【歴史ifシリーズ】とは?
あの時、日本が違う選択をしていたら――。本シリーズでは、歴史の分岐点で生まれたかもしれない“もう一つの未来”を物語として描きます。
本記事「エルピーダ救済編」は、現実とは異なる
フィクション(ifストーリー)です。史実の流れを確認したい方は、
導入編(倒産編)
をご覧ください。
【歴史ifシリーズ|エルピーダ救済編】もう一つの未来
プロローグ:分岐点の夜
2012年2月、永田町。会議室には緊張が張りつめていた。カーテンの隙間から差す街灯の光が、資料の束と疲れた顔を淡く照らす。
「これ以上の税金投入は国民に説明できない」――そう告げる声に、別の声が重なる。「だが、この企業が消えれば日本の半導体は終わる」。
現実の歴史では、不支援が決まった。だがもし、その夜に違う言葉が選ばれていたなら――。
第一章:決断 ― 国家の覚悟
「日本の半導体をここで終わらせるわけにはいかない」。首相の一言で空気が変わった。閣僚たちは短い沈黙ののち、うなずいた。
追加の公的資金、数千億円規模の救済が承認される。広島の工場に知らせが届くと、夜勤のフロアに小さな歓声が波紋のように広がった。「まだ戦える」。止まりかけた設備が再び鼓動を打ち始める。
第二章:アップルとの絆
クパチーノの会議室。アップルの幹部は日本政府の決断を歓迎した。「我々は安定供給を求めている。エルピーダの技術は不可欠だ」。
連携は一気に深まる。iPhoneやiPad、そして次世代のデバイスには「日本製DRAM」が搭載され、世界のユーザーが手にする端末の奥底で、エルピーダのチップが静かに輝いた。
若手エンジニアは家族に語る。「このチップは世界を動かす。俺たちが日本の未来を作っているんだ」。誇りは、過酷な改良と歩留まり改善の夜を支える燃料になった。
第三章:日の丸半導体連合
救済を「延命」で終わらせない。政府はそう腹をくくった。産業再編の号令とともに、エルピーダが中核となる“連合”構想が動き出す。
メモリとロジックの橋渡し。広島、東北、九州――全国の拠点がネットワーク化され、人と技術が行き交う。老練の職人技と、機械学習による最適化が同じ現場で溶けあっていく。
第四章:復活のシナリオ
2015年、エルピーダは20nm世代のモバイルDRAMを量産化。サムスンと並び立ち、ハイニックスを追い上げる。クラウド事業者向けの高帯域メモリでも存在感を増し、国際展示会では「ジャパン・イズ・バック」の見出しが躍った。
2017年、AI向けの大容量・高効率メモリを発表。学会と量産現場が直結した開発体制は、世界でも稀有だった。投資家は日本の半導体株を再評価し、街の家電量販店には「内側まで日本製」というコピーが並ぶ。
第五章:失われなかった30年
救済から10年。日本の半導体は世界シェアの二桁台を回復し、産業の裾野には新しい雇用とスタートアップが生まれた。「失われた30年」と呼ばれたはずの時代は、「再生の10年」と語られるようになる。
学生たちは誇らしげに言う。「日本のスマホは世界一だよ。だって中身が日本の技術でできているんだから」。その言葉は、かつて工場で夜を明かした技術者たちの胸に静かに刻まれた。
エピローグ:もう一つの未来
現実の歴史では、エルピーダは倒産し、マイクロンの一員として面影をつないだ。だが、もし救済されていたなら――日本の半導体は今も世界の最前線で輝いていたかもしれない。
過去は変えられない。だが未来は、まだ選べる。 選ばれなかった道を想像することは、次の選択を賢くするためのリハーサルでもあるのだ。
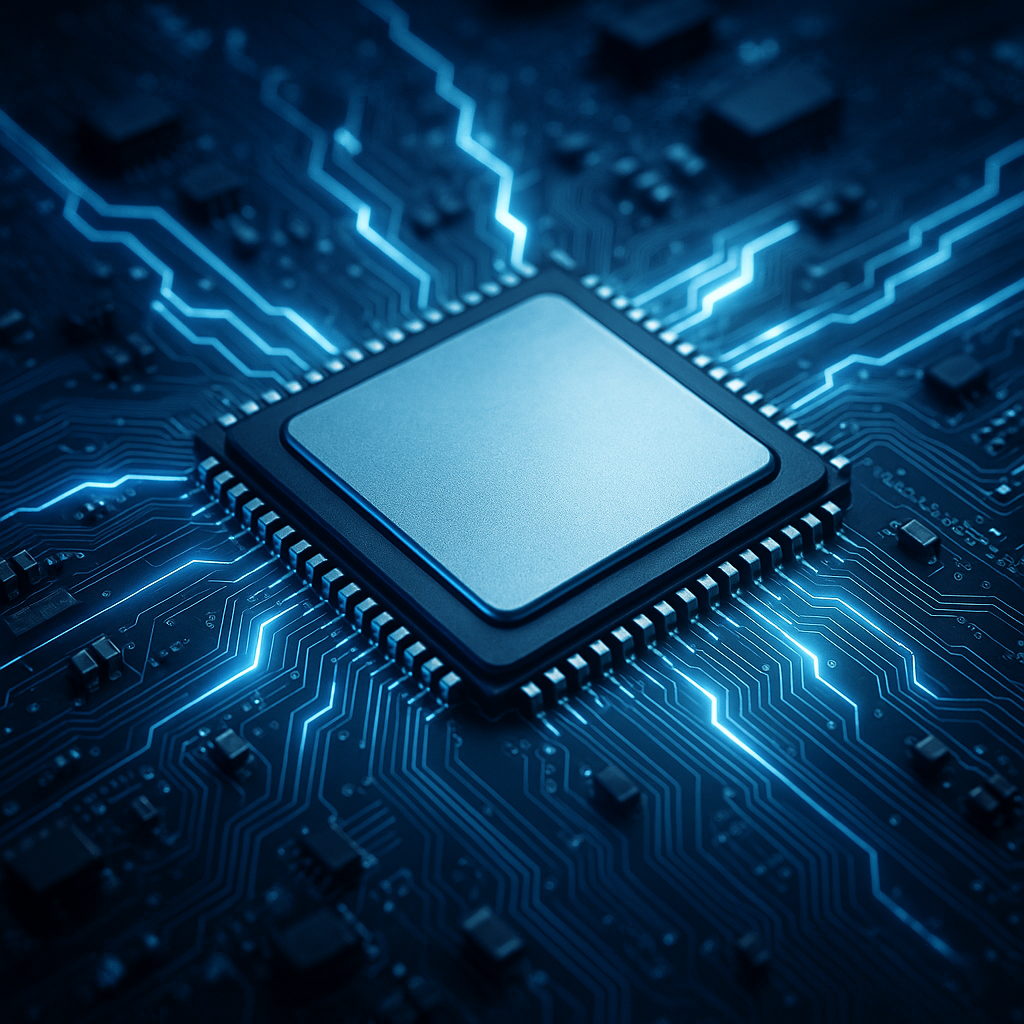
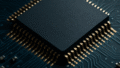

コメント