【歴史ifシリーズ】とは?
あの時、日本が違う選択をしていたら――。本シリーズでは、歴史の分岐点で生まれたかもしれない“もう一つの未来”を物語として描きます。
本記事「エルピーダ倒産編」は、事実に基づき再構成した導入編です。次回の
「救済編」では、この現実とは異なる
フィクション(ifストーリー)をお届けします。
※一部に臨場感を高める演出を含みます。
【エルピーダ倒産編】日本半導体の灯が消えた日
プロローグ:衝撃の速報
2012年2月27日午前9時。テレビ画面に速報が流れた。
「エルピーダメモリ、会社更生法を申請」
その瞬間、広島工場の社員食堂に沈黙が広がった。白衣を着た技術者たちは箸を止め、画面に釘付けになった。誰も言葉を発しない。日本が「半導体メモリ」という巨大市場から姿を消すことを、誰もが悟っていたからだ。
第一章:誕生 ― 希望を託された企業
1990年代後半、日本の半導体は急速に衰退していた。かつて世界を席巻したNEC、日立、三菱も、韓国サムスンに追い抜かれつつあった。
「このままでは日本は消える」――そう危機感を抱いた政府と産業界は、統合を選んだ。1999年、NECと日立がDRAM事業を統合。翌2000年には三菱も加わり、新会社が誕生した。
社名は「エルピーダメモリ」。ギリシャ語で「希望」を意味する。日本最後のDRAM専業メーカーとして、「日の丸半導体の最後の砦」と呼ばれた。
第二章:技術者たちの誇り
エルピーダの広島工場は、世界最先端の技術拠点だった。2009年には30nm級DRAMを世界に先駆けて量産化。さらにアップルと関係を深め、iPhone向けモバイルDRAMを供給する大きな役割を担った。
アップルは当時、サムスンへの依存を減らす戦略を進めていた。その流れでエルピーダやハイニックスに注目し、調達先を拡大していった。エルピーダの売上の多くは、やがてアップルとの取引に依存するようになった。
工場の現場では、技術者たちが誇りを胸に語り合った。「このチップが世界中のスマホを動かしているんだ」。しかし、その誇りの裏に潜むリスクを、誰も完全には否定できなかった。
第三章:資本力の壁
サムスンとハイニックスは国家支援を背に、巨額の投資でコストを徹底的に下げた。一方、エルピーダは資金調達で大きく劣り、世界的な価格競争に耐えきれなかった。
2008年のリーマンショック後、DRAM価格は暴落。さらに1ドル=80円を切る超円高が収益を直撃した。
「技術では勝っているのに、資金では勝てない」――それが、現場の技術者たちの共通した思いだった。
第四章:希望の光と影
2009年、政府の産業再生法による公的資金注入で一度は救済された。広島工場では新しいラインが稼働し、アップル向けの製品を大量に出荷。社員の間に「まだやれる」という希望が広がった。
だが、その希望は長く続かなかった。アップルへの依存は重く、価格交渉では常に不利に立たされた。「アップル向けを失えば、会社は持たない」――その不安は誰もが抱いていた。
クライマックス:永田町の冷たい夜
2012年初頭、永田町の会議室。閣僚と官僚たちが追加支援の是非を巡って激しく議論した。
「これ以上の税金投入は国民に説明できない」/「ゾンビ企業を延命させるのか?」/「だが、この企業が倒れれば、日本はDRAMから完全に退場だ!」
声が飛び交う中、最終的に下された結論は――不支援。東日本大震災からの復興財源が優先され、産業政策としての支援は切り捨てられた。
その夜、広島工場の技術者たちは黙って機械を見つめた。胸の奥で「もう終わるのか」という予感を抱きながら。
エピローグ:消えた希望
2012年2月27日。エルピーダメモリは会社更生法を申請。負債総額4,480億円。製造業としては戦後最大級の倒産だった。
数か月後、米マイクロンが買収を発表。エルピーダの技術と人材は「マイクロン・メモリ・ジャパン」として生き延びたが、「希望」という名を持つ会社は、この日を境に歴史から姿を消した。
日本はDRAM市場から完全に撤退し、その地位は韓国と米国が独占することになった。
教訓
エルピーダの倒産は、日本半導体の衰退を象徴する事件だった。技術力だけでは産業は守れない。資金と政治の覚悟がなければ、世界では生き残れない。
この現実を知った上でこそ、次に語られる 「もし救済されていたら」 という物語が輝きを増すのだ。
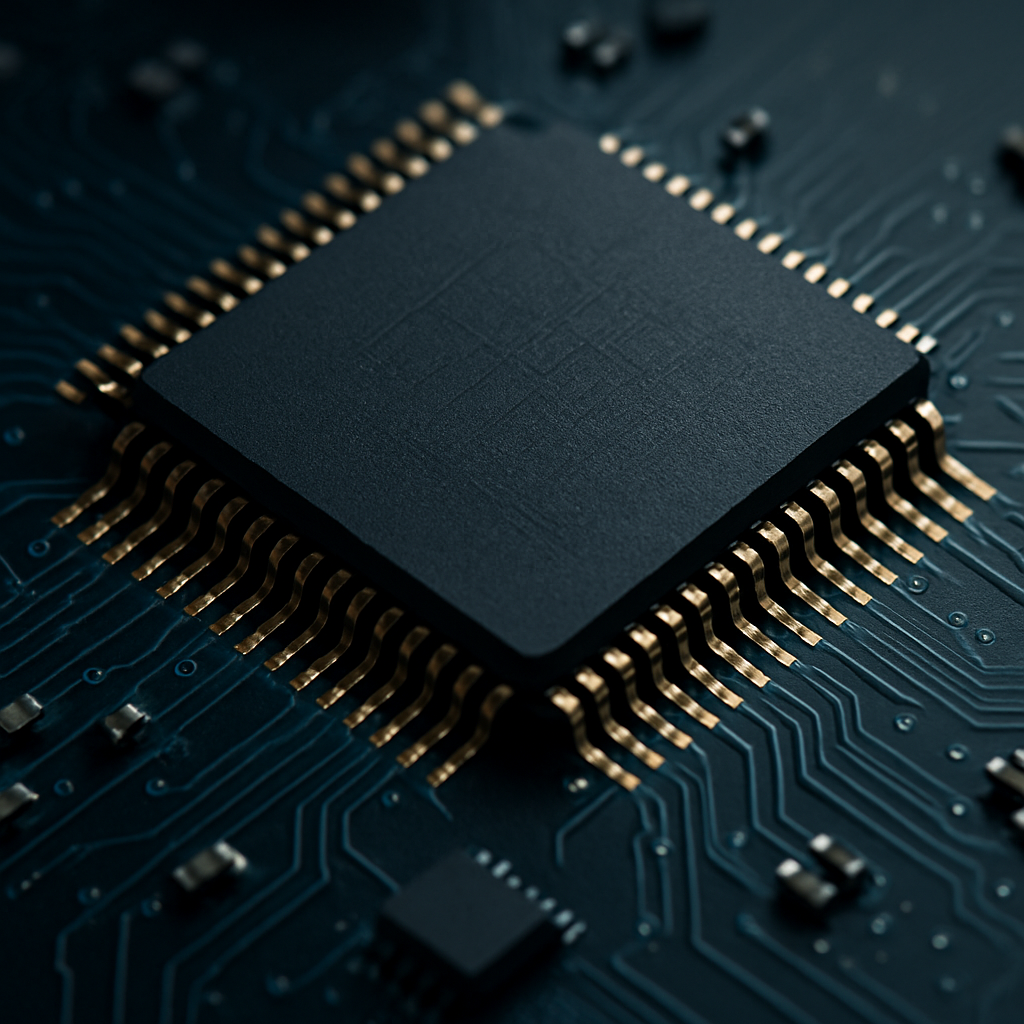


コメント