こんにちは。haretomaJOURNAL管理人の晴れとまとです。
皆さんは日産車はお好きですか?最近は目立ったヒット車が少ないものの、GT-RやフェアレディZなど根強い人気を誇るモデルもあります。
しかし、その日産もいまや経営難に陥っています。
そしてその転換点となったのが、カルロス・ゴーンの逮捕でした。もしあの逮捕がなければ、日産はどうなっていたのでしょうか。
今回の「歴史if」では、逮捕されなかった場合の“もしも”の世界を描いてみたいと思います。
プロローグ:2018年11月19日、衝撃のニュース
——2018年11月19日、羽田空港に到着したカルロス・ゴーンは東京地検特捜部に任意同行を求められ、その日のうちに逮捕された。
「日産会長逮捕」というニュースは瞬く間に世界を駆け巡り、日本の自動車産業の地殻変動が始まった。
罪状は二つ。
- 金融商品取引法違反(報酬の過少記載)
- 会社法違反(特別背任)
事件はガバナンスの問題をあぶり出し、アライアンスの舵取りを大きく変えることになる。
第1章:現実の世界(ゴーン不在後の日産)
ゴーンが去った後、日産は「自主独立」を掲げ、日本企業としての看板を守る道を選んだ。
しかしEV市場ではテスラや中国のBYDが急成長し、ホンダとのEV提携も2025年に解消。
国内外の販売台数は伸び悩み、業績は苦しいままだった。
守ったものは確かにあったが、競争力という代償は重かった。
第2章:ifの世界(ゴーンは逮捕されなかった世界)
ゴーンは壇上に立ち、ルノー・日産・三菱の完全統合を宣言する。
「われわれは世界第1位の自動車グループを目指す!」
その言葉どおり、アライアンスは巨額投資でEVとソフトウェアに総力戦を展開。
リーフの後継群は計画どおり立て続けに投入され、日産はテスラに並ぶ存在へと成長した。
供給網の一体最適化、共通アーキテクチャの徹底、調達力の強化——統合の果実は早期に現れた。
だが、加速の陰で歪みが広がる。意思決定の重心は欧州に移り、日本市場に根差した開発とブランド発信は弱まる。
モデルチェンジの間延びやヒット車不足が続き、競争力は徐々に失われた。
「世界1位」を掲げた連合は、やがて市場の変化速度に追いつけず、業績は悪化へと転じていった。
第3章:結末が重なる理由——根本的な課題
ifの未来でも、現実の未来でも、行き着く壁は同じだった。そこには事件の有無を超えた 日産の根本課題が横たわっている。
- 経営判断の遅さ:役員合議に頼り、意思決定に時間がかかる。新型車投入の遅れが競争力を奪った。
- ブランド力の弱体化:「技術の日産」の看板が色あせ、トヨタやホンダのような圧倒的ヒット車に欠ける。
- EV戦略の失速:量産EV「リーフ」で先行したのに、後続展開が遅れ、海外勢に追い抜かれた。
- アライアンス依存構造:連合の論理が優先され、日本独自の戦略が輪郭を失った。
事件があってもなくても、この課題を克服できなければ未来は同じだったのかもしれない。
エピローグ:二つの世界から見えるもの
カルロス・ゴーン事件は、日産に二つの未来を示した。
ひとつは——ゴーンの下で「世界1位を狙う未来」。
だが統合の果てに、日本企業としての独立性を失い、やがて業績も悪化した。
もうひとつは——ゴーンを失い「独立を守った現実の未来」。
だが競争力を失い、経営難に苦しむ姿だった。
どちらを選んでも茨の道。
しかしそれは、日産が持つ「可能性」を否定するものではない。
かつて危機から立ち直ったように、再び“技術の日産”を掲げ、EVや次世代モビリティで挑戦することはできる。
歴史ifが示したのは、未来を諦める理由ではなく、再生への道を探すきっかけなのかもしれない。
これからの日産の挑戦に期待したい。
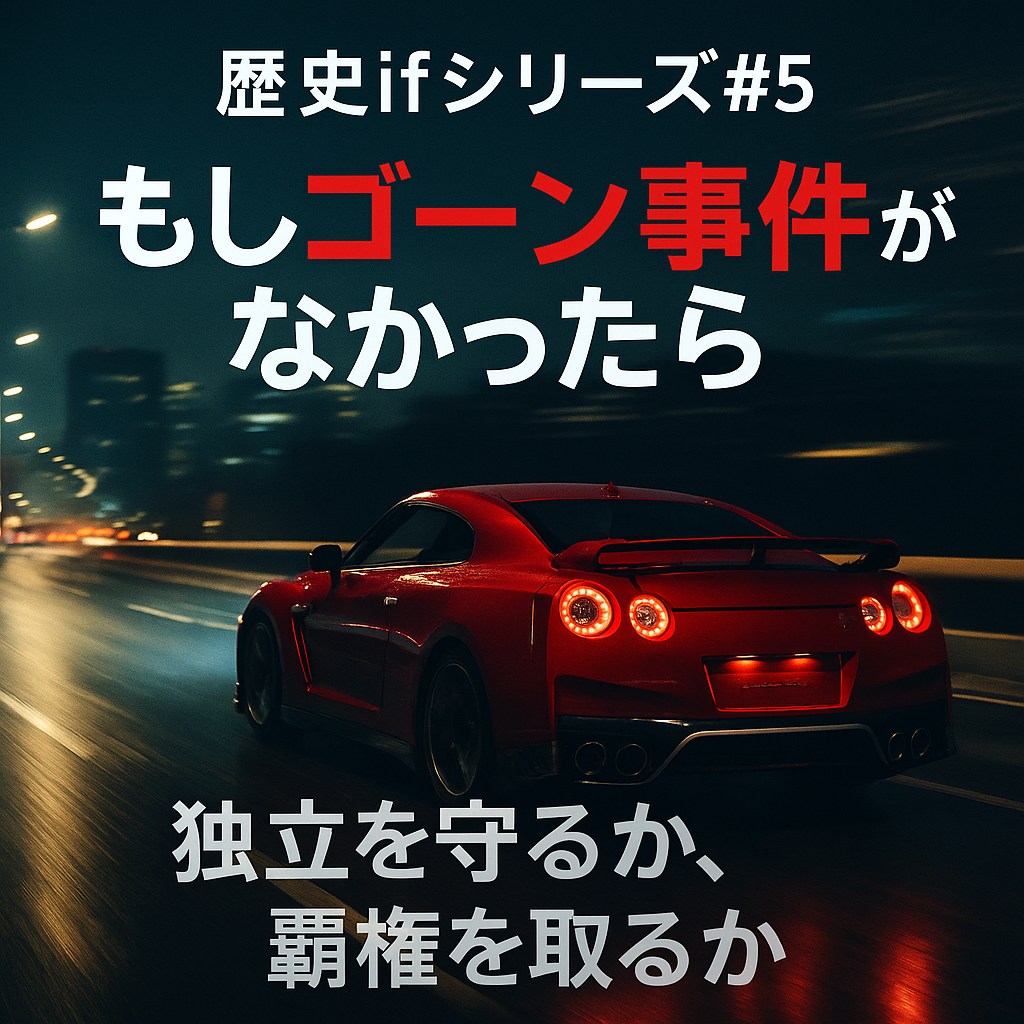

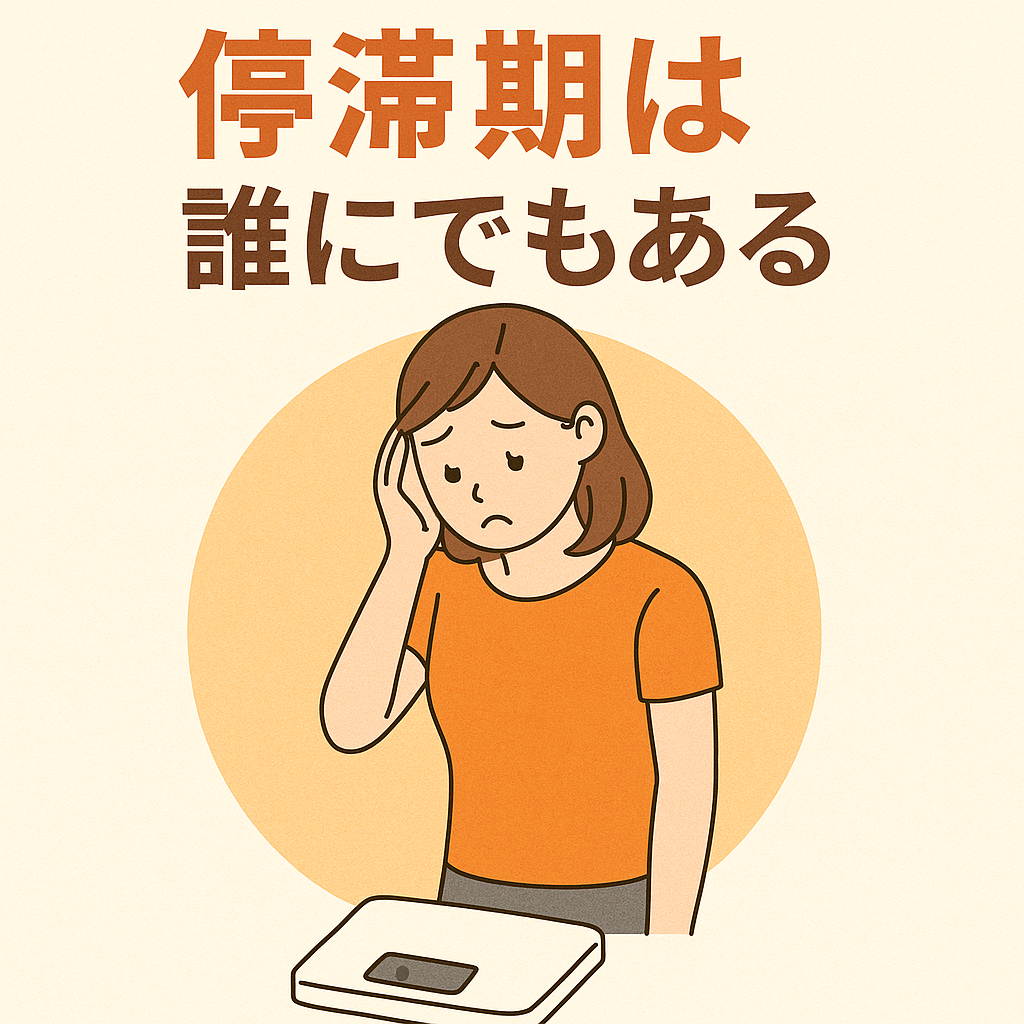
コメント