皆さんこんにちは。haretoma JOURNALの晴れとまとです。
「食事制限も運動も頑張っているのに、体重が全然減らない…」そんな経験をしたことはありませんか?
実はこれは、誰もが一度は通る道です。努力が足りないからでも、方法が間違っているからでもなく、体の仕組みがそうさせているのです。
そして、停滞期の原因を知らないと「もっと食事を減らさなきゃ」「もっと運動しなきゃ」と無理に頑張りすぎてしまい、精神衛生上も良くありません。結果として続けることができなくなり、せっかくの努力が台無しになることもあります。
そこで今回は、ダイエット中に体重が落ちにくくなる「停滞期」の原因を詳しく解説します。
停滞期とは?
ダイエットを始めた直後は、食事量を減らすだけで体重がスルスル落ちることも多いです。しかし数週間~1か月ほど経つと、減少スピードが落ちてきて、ある日からまったく動かなくなる…。この状態を「停滞期」と呼びます。
停滞期は決して異常ではなく、むしろ体が生命を守るために働いている証拠です。この仕組みの背景には、「ホメオスタシス(恒常性維持機能)」という体の防御反応があります。
なぜ体重が落ちにくくなるのか?主な4つの原因
1. 代謝が落ちる(ホメオスタシスの働き)
人間の体は「急激な変化」を嫌います。体重が短期間で減ると「飢餓の危機だ!」と判断し、できるだけエネルギーを使わないようにします。これにより、同じ運動や食事制限を続けていても、消費カロリーが以前より少なくなるのです。
言い換えれば、体は「省エネモード」に切り替わっているのです。これは人類が生き延びるために備わった機能で、太古の昔、食糧不足の時代には欠かせない仕組みでした。
2. 筋肉量の減少
極端に食事量を減らすと、脂肪だけでなく筋肉も落ちてしまいます。筋肉は「基礎代謝」を大きく左右しているため、減れば減るほど脂肪を燃やしにくい体になります。
特にたんぱく質の摂取が不足していると、体は筋肉を分解してエネルギーに変えてしまいます。「カロリーは減っているのに体重が落ちない…」という人の中には、この筋肉量の低下が大きな要因になっている場合も多いのです。
3. 水分やグリコーゲンの変動
体重の増減は、脂肪だけでなく「水分」や「グリコーゲン(体内に貯蔵される糖質)」の量にも影響されます。
例えば炭水化物を減らした食事をすると、最初はグリコーゲンと一緒に水分が抜けるため、急激に体重が落ちます。しかしその後は脂肪だけが落ちていく段階になり、変化がゆるやかになります。
「昨日より500g増えた!」と一喜一憂してしまいがちですが、そのほとんどは水分量の差であり、脂肪が急に増えたわけではありません。
4. ストレスや睡眠不足
意外に見落とされやすいのが、ストレスや睡眠不足です。これらが続くと、体内で「コルチゾール」というホルモンが増え、脂肪燃焼が妨げられることが分かっています。
また、寝不足になると食欲を抑えるホルモン「レプチン」が減り、逆に食欲を刺激する「グレリン」が増えることも知られています。その結果、つい食べすぎてしまい、ダイエットが停滞する原因になるのです。
停滞期は「努力が無駄になっている」わけではない
体重が落ちなくなると、多くの人は「もっと食事を減らさなきゃ」「運動を増やさなきゃ」と考えがちです。しかし、過度な制限は筋肉を減らしたり、リバウンドを招いたりと逆効果になることもあります。
停滞期は「体が頑張っている証拠」であり、むしろ正常な反応です。大切なのは、この時期を「焦らず」「工夫して」乗り越えること。
まとめ
ダイエットを続けているのに体重が落ちにくいのは、あなたの努力不足ではありません。体はとても賢く、環境に合わせてバランスを保とうとします。
- ホメオスタシスによる代謝低下
- 筋肉量の減少
- 水分やグリコーゲンの変動
- ストレスや睡眠不足
これらが重なり合って、体重が落ちにくくなるのです。
次回は、この「停滞期」をどう乗り越えればいいのか。実践できる解決策を紹介していきます。あなたの努力は必ず実を結びます。一緒に続けていきましょう!
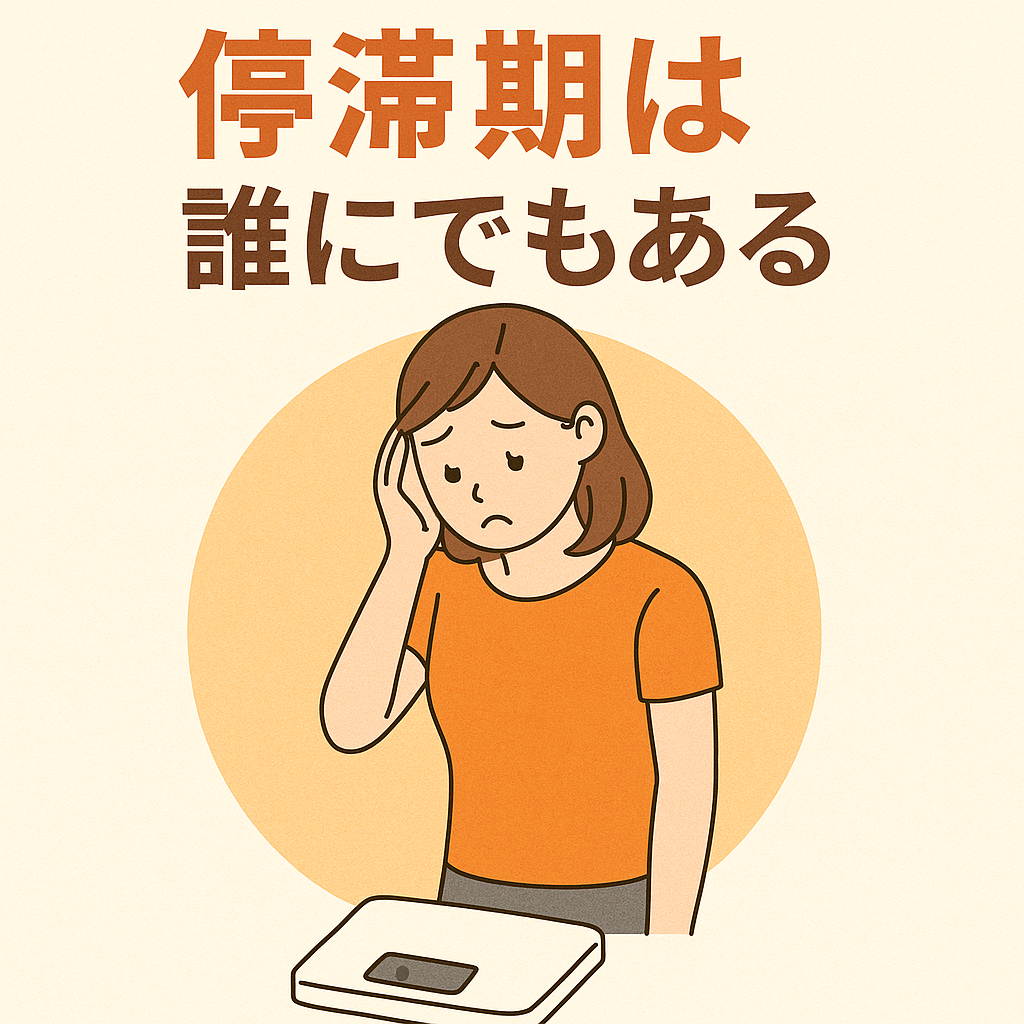
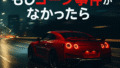

コメント